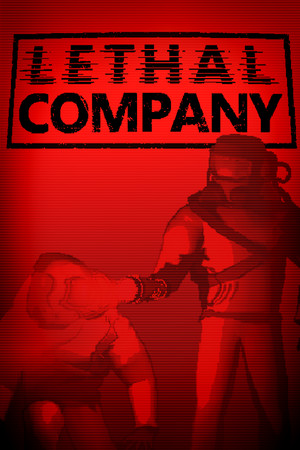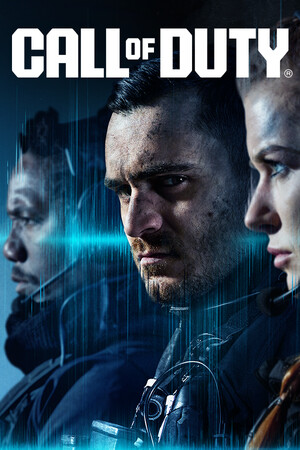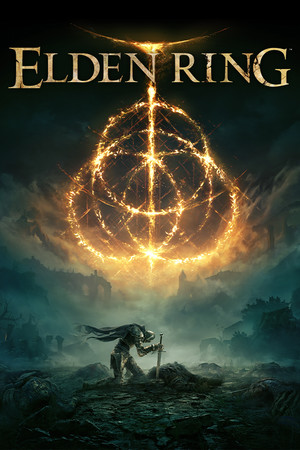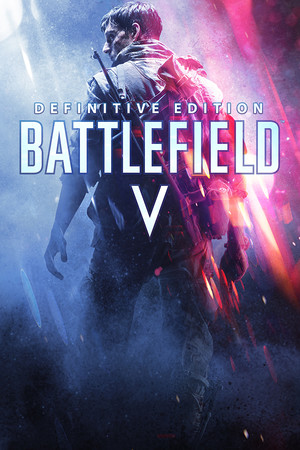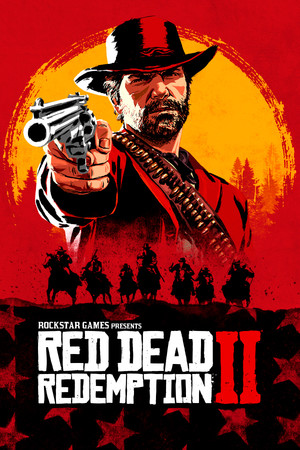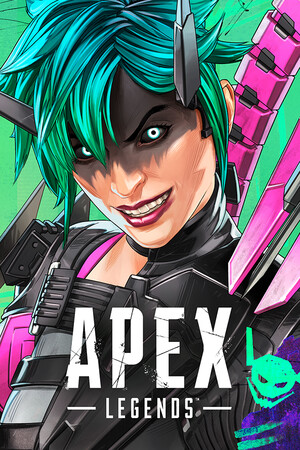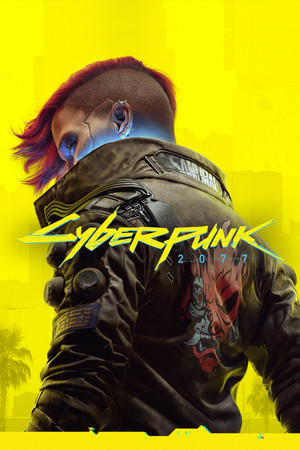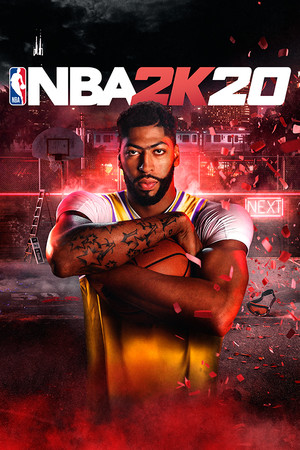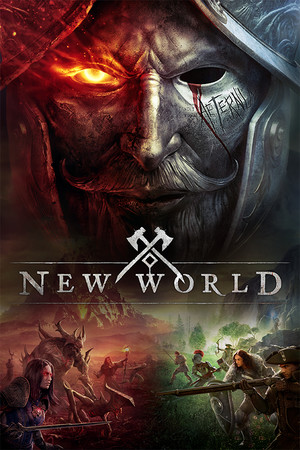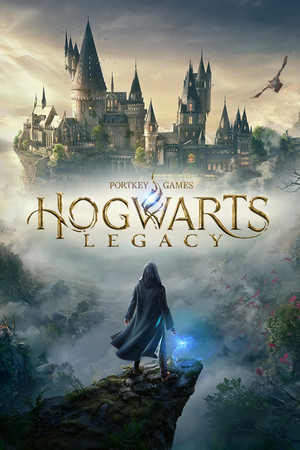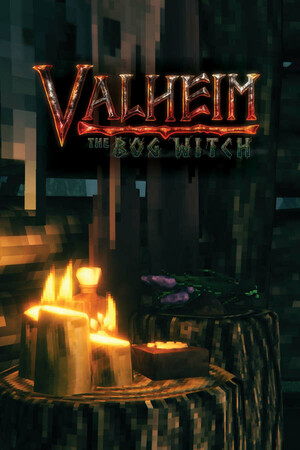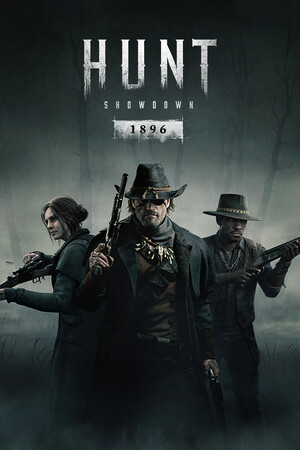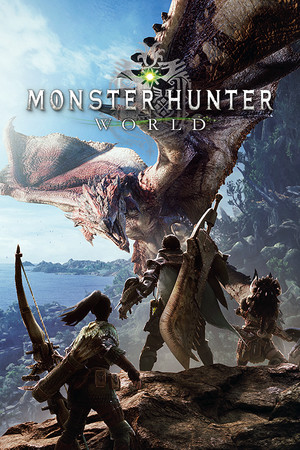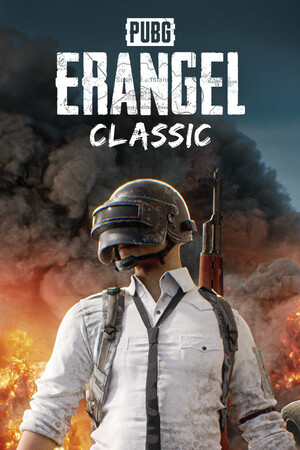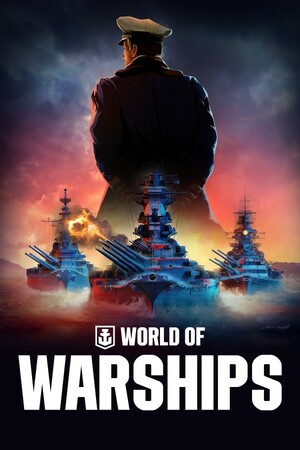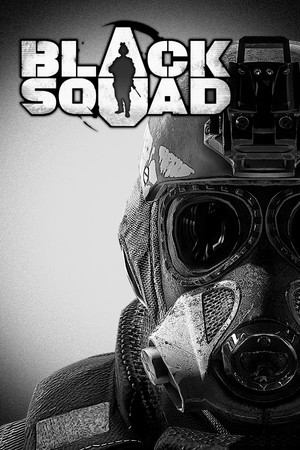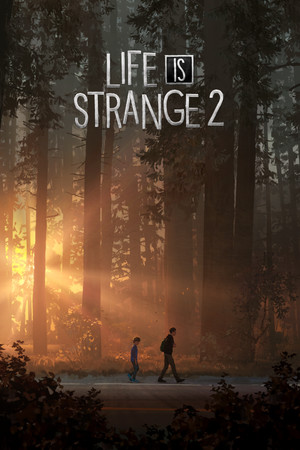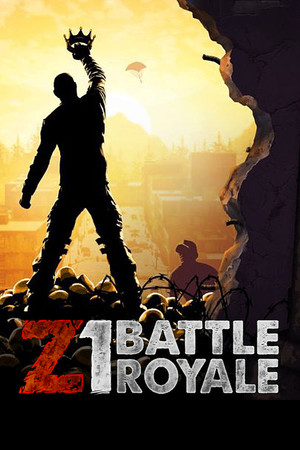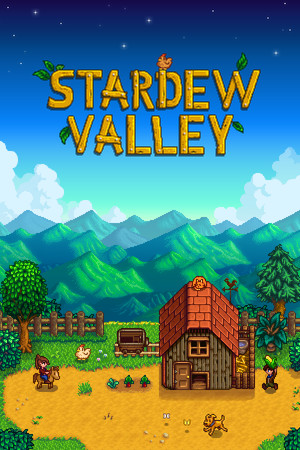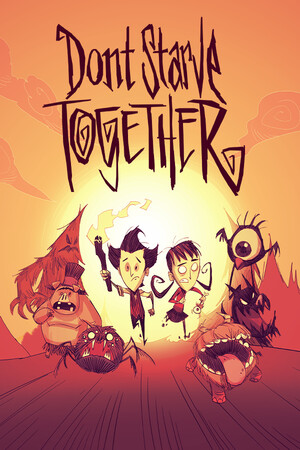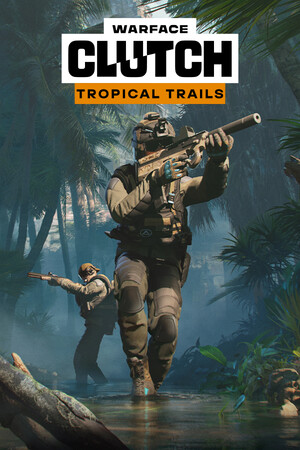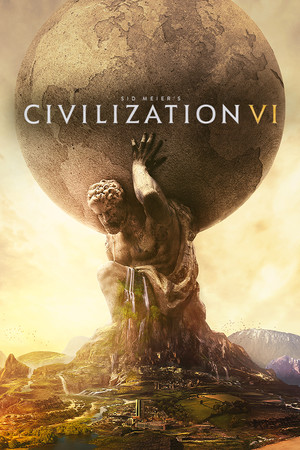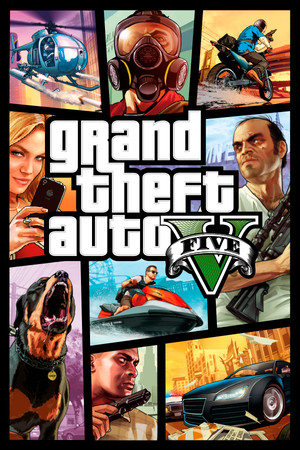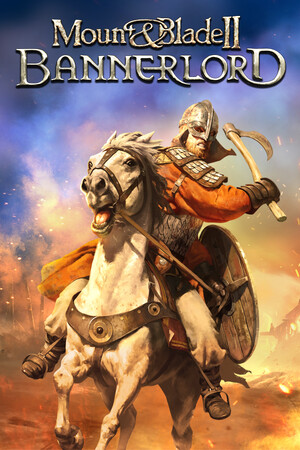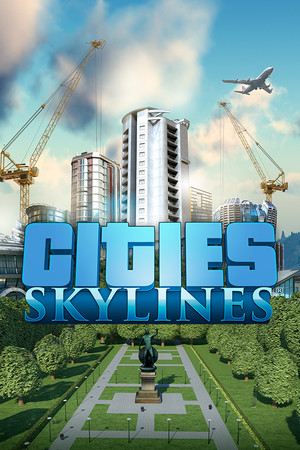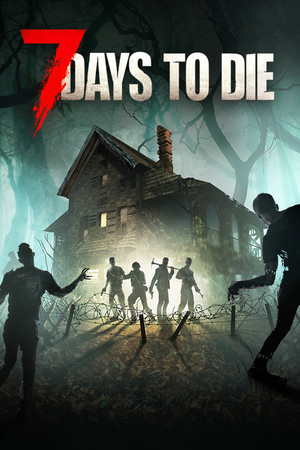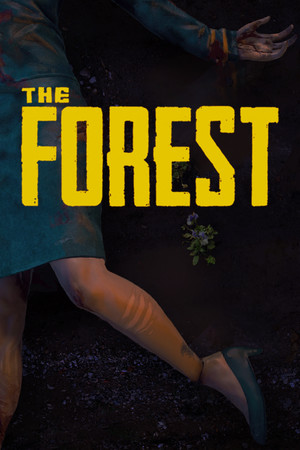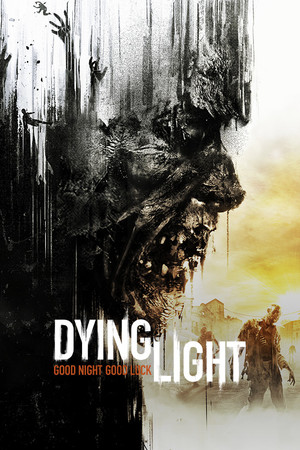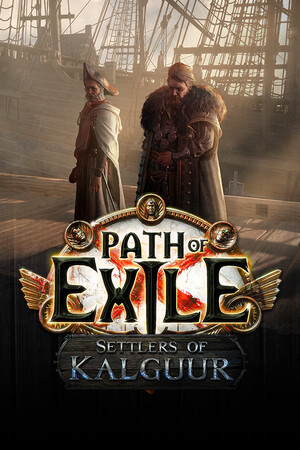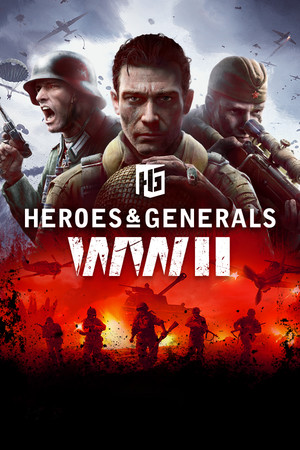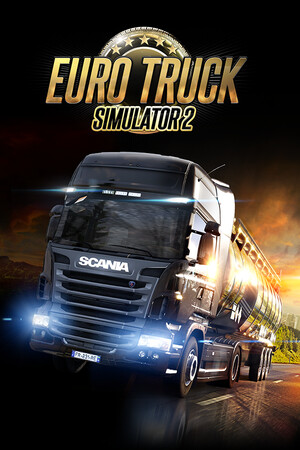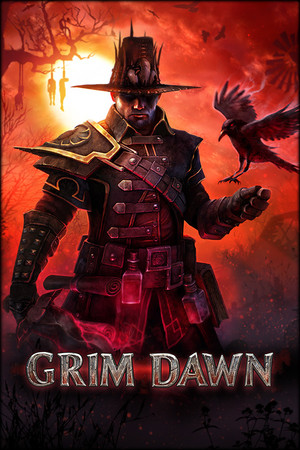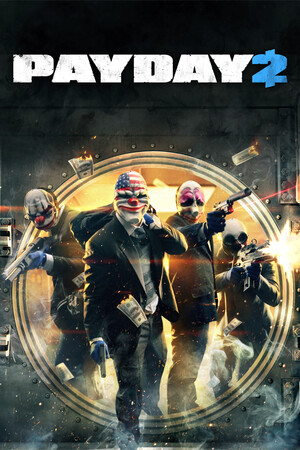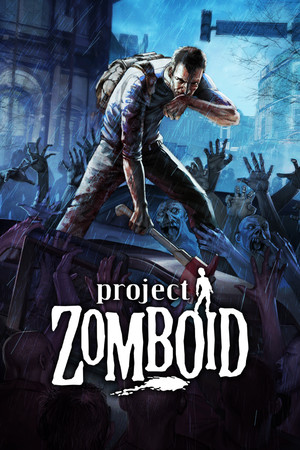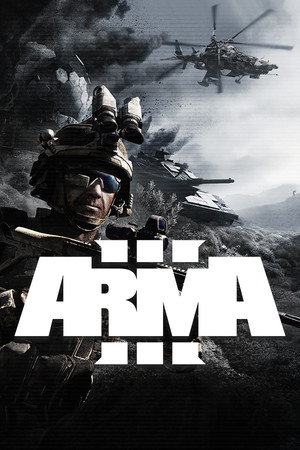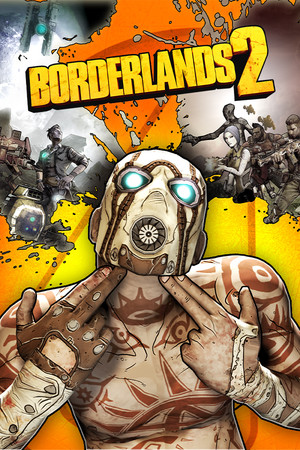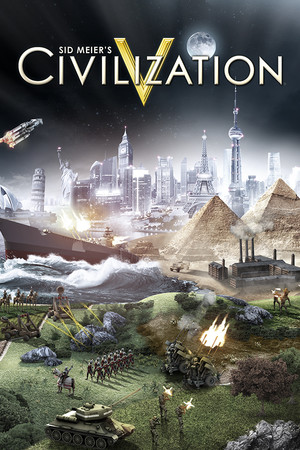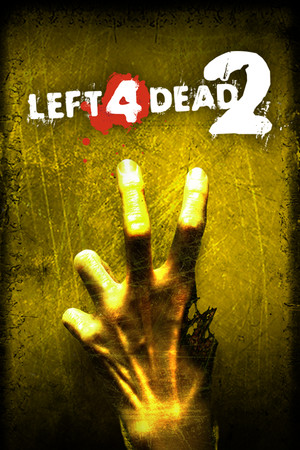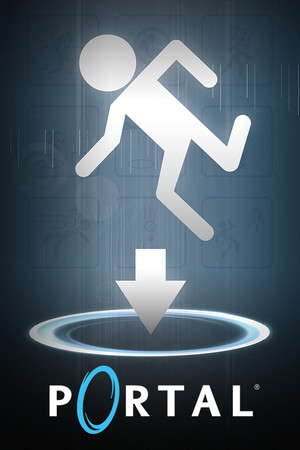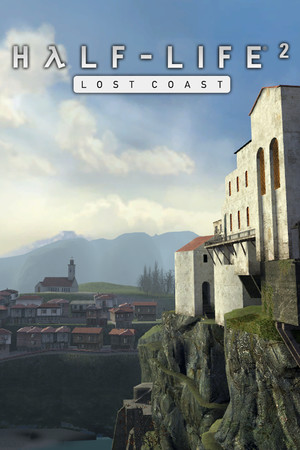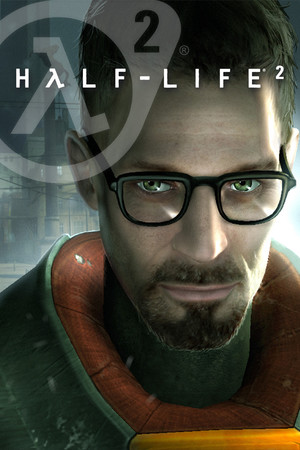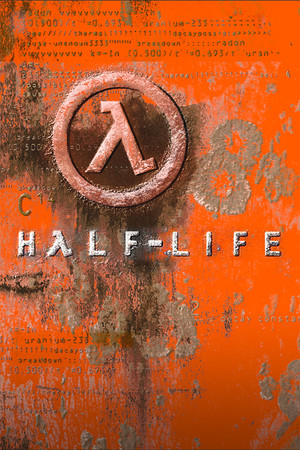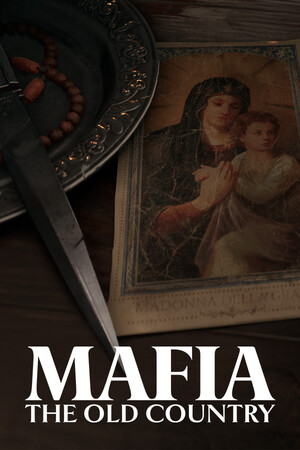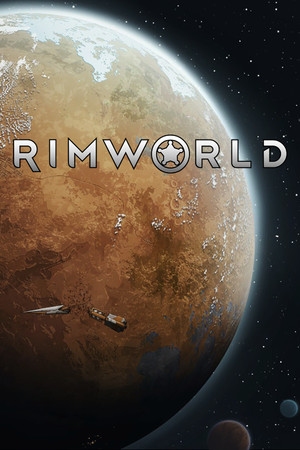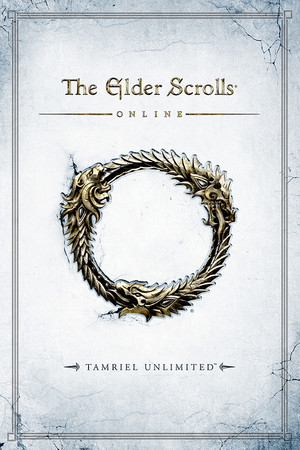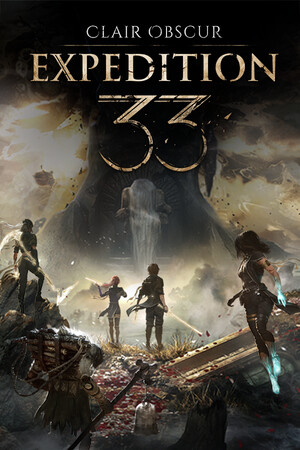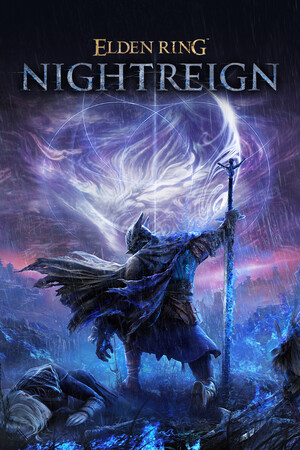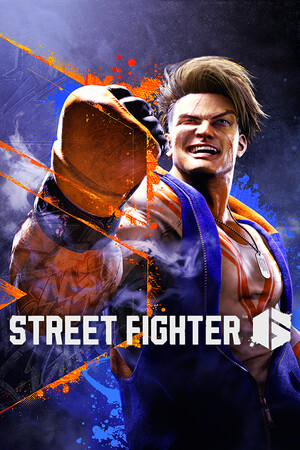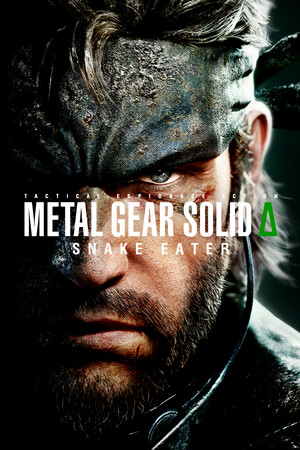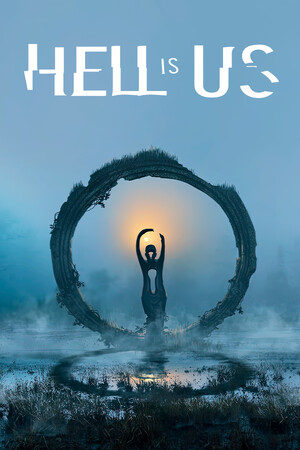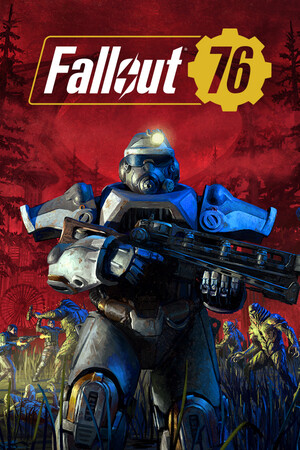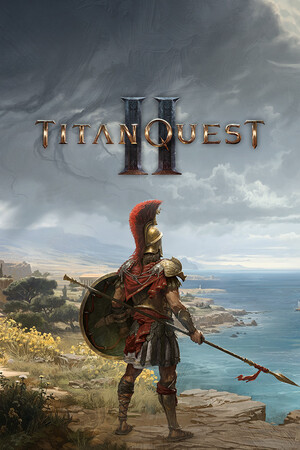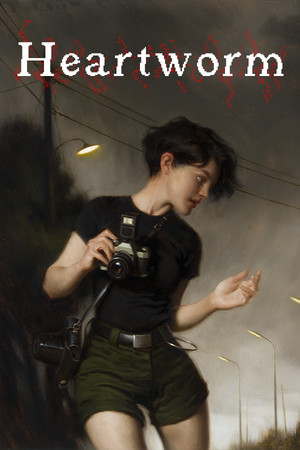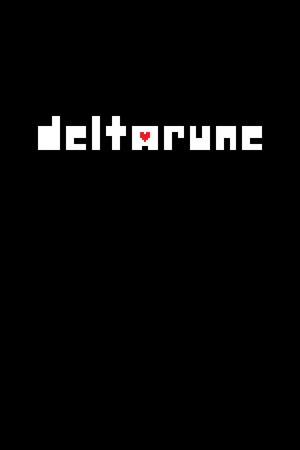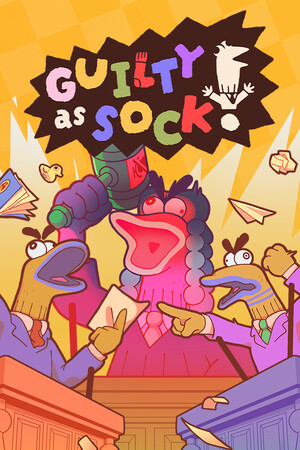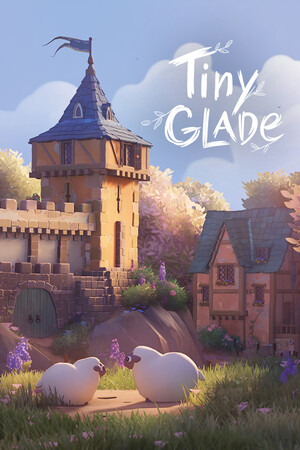Cronos: The New Dawn
 Sep 5, 2025
Sep 5, 2025 Sep 3, 2025
Sep 3, 2025 Sep 5, 2025
Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
Sep 4, 2025

76561199004086690
Not Recommended16 hrs played (5 hrs at review)
面白いんですが
改善点が多いですかね。
2 votes funny
76561197993473791
Recommended19 hrs played (19 hrs at review)
一部の環境で発生する再現性の高いバグを発見したので回避方法を先に書いておきます。
【フリーズバグの回避方法】
①:『音声ログ再生時のフリーズ』
・音声ログを拾ってすぐにログの再生をキャンセル/終了する事で回避可能。
②:『出口(ファストトラベル)に戻る時のフリーズ』
・使用せずに歩いて戻る(戻れる場合)
※上記で回避できない場合は言語を一旦英語に変更でいけるはず!
こちらはアドバンスドアクセスで発生しているバグなので、すぐに修正されると思いますが、参考になれば何よりです。
ぜひ楽しんでください!
我らが使命によりて。
----
Flydigi Direwolf 2コントローラーを使用。
プレイ動画をアップしているので、本作が気になった方はこちらを参考までにどうぞ。https://www.youtube.com/watch?v=s93uMOyOVPU
あらすじとゲーム概要
◆ 「SILENT HILL 2(リメイク版)」や「The Medium」で知られる開発元の贈る、三人称視点のSFサバイバルホラー作品。 東欧の残忍性とレトロフューチャーテクノロジーが融合した過酷な世界を舞台に、ねじれたタイムトラベル、過去と未来を行き来する手に汗握るストーリーが展開される。 プレイヤーは謎に包まれた共同体のエージェントとして旅し、80年代のポーランドに連れ戻す特殊な時間の裂け目を見つけるため、未来の荒れ地を捜索するという任務を請け負う。 荒廃した未来の世界で戦い抜き、悪夢のように融合するクリーチャーが出現した理由、人類を滅ぼした黙示録の真相を探るため、時を遡って魂を狩れ。 物語や演出面では「エイリアン」シリーズや「遊星からの物体X」などの古典的名作から影響を受けているようで、レトロフューチャーな表現だけではなく、当時のボディホラーを彷彿とさせる映像表現も登場する。 さらに開発元が本作の舞台であるポーランド出身という事もあり、80年代のポーランド、共産党支配の抑圧、労働者/市民による抵抗、経済危機と社会不安、冷戦期の東欧の中でもとりわけ激動に満ちた時代の“その場所”の表現が非常に上手く取り入れらている。 アクションやシステム面に関しては、各項目でそれぞれ詳細に解説するが、本作はシステム面で「Dead Space」シリーズから強く影響を受けているだけではなく、三人称視点のシューター要素、敵を殴る/踏みつける、敵を燃やす、探索周り、硬派なインベントリ管理、装備の強化要素などなど、全体的に「Dead Space」、「SILENT HILL 2(リメイク版)」、「サイコブレイク」等の同ジャンルの名作のシステムを、良い意味で、ミックスした内容となっている。戦闘システム
◆ 基本的な攻撃用のアクションは銃を撃つ、殴る/踏み付けるとなるが、この他に自身の周りを燃やすトーチ、敵に爆弾を設置するパイヤーなども物語を進める事で使用可能となる。 初期から主人公が使用可能である銃「ソード」、ピストル的な性能のこの銃は非常に優秀で、チャージする事によって威力が上昇し、さらに敵を貫通するようになる。 探索を通じでショットガン、アサルトライフルの様な銃などを入手できるが、このチャージを利用したアクションは本作の殆どの武器で使用できるので、慣れておくと良いだろう。 ちなみに、武器の総数自体は少ないが、それぞれでしっかりと状況によって“使える”ため、あまり気になる事は無いはずだ。 同ジャンルの他の作品と同様に、敵の足などの部位を撃ち抜くことで転ばせるといった事が可能で、転んだ敵に踏みつけでダメージを与えて弾薬を節約するといった事も勿論可能だ。 ただし、注意点としては、初期状態の主人公の近接攻撃は威力が非常に弱いため、ある程度敵のHPの残量を把握していないと起き上がった敵から逆にダメージをもらってしまう可能性がある。 ネタバレになってしまうため詳細は控えるが、物語/探索を進める事で近接攻撃の威力を上昇させる事ができるので、そちらを有効活用すると良いだろう。 部位を攻撃する事はもちろん、本作の特徴ともいえる武器の「チャージ」を絡めた戦闘は独特で面白く、チャージを行う必要がある戦闘では、同ジャンルの他の作品とは別の意味で敵との間合いの取り合いや、チャージにかかる時間の把握、そういった部分が重要となり、プレイヤースキルが問われる箇所がある点が魅力的だ 少し話がズレるが、敵の部位を狙うと言えば、エイム時の本作の主人公は禁断症状のヤ○中患者の如く手が震えるため、後ほど解説する武器の強化である程度は「安定性」の強化を行う事をオススメする。 話を戻そう。 この他にも、「トーチ」と呼ばれる自身の周りに炎を発生させる武器も存在し、こちらの弾薬は「一つ」まで、セーブポイントで無料で補充可能となっている。 本作に登場する敵は他の敵の死体と融合し、より強力な敵へと変貌する。 それを発生させないためには死体を燃やす必要があり、トーチはそういった死体処理にも使用可能だ。 だが、実際にはトーチ使用中はちょっとした無敵時間が発生する事と、ボスを含め、殆どの敵は炎の影響で一時的に「スタン(のような)」状態になるため、緊急時やまとめて敵を撃破したい時等に、いわゆる「ボム」の様に使用される事が多い。 少し“コツ”の様な話になるが、セーブポイントに戻る事でトーチを補充できるため、時間はかかるが、一部のエリアではそれを悪用して楽に進める事も可能だ。 また、敵はセーブポイントに入れない仕様になっているので、扉の前まで連れて行き、そちらの仕様もついでに悪用すると良いだろう。 本題に戻ろう。 トーチ以外では物語の中盤で「パイヤー」と呼ばれる発射できる接着型爆弾も使用できる。 基本的にはトーチと同じように使用する形となっているが、こちらは拠点で補充されないため、弾薬を見つけるか、自身で作成する必要がある。 戦闘に関連した要素としては、戦闘が発生するエリア/レベルデザインも秀逸で、地形を上手く利用、活かすことによって楽に敵を撃破できたり、弾薬を節約する事ができる。 エリアの様々な箇所に配置されたオブジェクトの利用や、時間を巻き戻す能力を利用して爆発するオブジェクトを“再生”し、敵をおびき寄せてまとめて倒すといった事が可能だ。 ちなみに、本作の主人公は爆発に巻き込まれてもダメージを負わない仕様となっているので、殴ったり踏みつけによってこれらのオブジェクトを起爆すると弾薬を節約する事が可能だ。 こうったプレイヤー側意外の要素としては、敵のAIがなかなか優秀である点も本作の魅力と言えるだろう。 もちろんゲームであるため悪用したり、妙な地形に敵を嵌めるといった事も可能ではあるが、敵はある程度マップの地形を把握しており、最短距離でプレイヤーを狙う、先に死体と融合をしようとする、などと単調にならないような挙動を取ってくる。 そのため、プレイヤー側は敵の位置の把握や融合の阻止といった、攻撃以外の面でも頭を使う必要が出てくる。 特に後半は、同時に出現する敵の数も多くなるため、その点でもさらに面白くなってくる。 戦闘が発生するエリアも様々なモノが登場し、迷宮の様に複数の道が繋がる狭い閉塞的な空間、一本道の長い廊下、砂嵐によって視界の悪い場所、非常に広くて何処から敵が出現するか分からない場所などなど、プレイヤーを飽きさせない工夫がゲームの最後まで為されている。 戦闘面における人を選ぶ点も挙げるならば、主人公の動きがやや“重たい事”だろう。 主人公は重量級のスーツを着込んでいるのでそれが自然ではあるが、同ジャンルの他作品と比べて動きが遅く、また回避アクションも存在しないので、プレイヤーによっては違和感を覚えるかもしれない。 ただし、それによって理不尽なシチュエーションが発生するという事はなく、その動きを前提としたエリア構成/レベルデザインが為されている。探索とマップ作り
◆ レトロフューチャー感漂う歪にねじれ、荒廃したダークな未来世界。 次元の裂け目を通じて訪れる事の可能な、日常の風景が垣間見えるが、明らかに異常な何かが浸食を始めている80年代のポーランド。 そういったギャップの魅せ方が上手く、ビジュアル面でも非常に魅力的となっている。 「The Medium」の開発元だけあり、一瞬で場面、地形などが変化するといった演出も非常に上手い。 別の項目で述べた戦闘が発生するエリアの作りの巧さもさることながら、探索周りに関しては、しっかりとプレイヤーが探索を行う事によって隠された部屋やエリアを発見することができ、その中には様々な有用なアイテムが配置されていたりと、探索する面白さ、発見する楽しさ、そういった要素を良く理解した作りだ。 探索時に注意する必要がある点としては、初期状態では、インベントリの枠が非常に少ない事だ。 そのため、多くの弾薬や回復薬を持ち歩くと、探索時に発見したアイテムを回収できないという事態が発生する。 殆どの場所には再び立ち寄る事ができるが、何か所かは戻れないので、探索時にはその点に注意すると良いだろう。 それに加えて、後ほど解説する強化によってインベントリの枠を拡張できるため、そちらを優先的に行う事をオススメする。 注意点と言えば、同ジャンルの他の作品がそうであるように、本作では物語の進行や探索時にいくつかのパズルが登場するが、必要最低限、さらに簡単なモノとなっている。 登場するパズル要素は、アイテムの配置系、パスワード系などの良く見るものから、特定の物体の時間を巻き戻して通行可能にする、物語を進める事で入手できる磁力を利用したブーツを使用して特殊な足場へと“飛び回る”モノや、特殊な弾を利用した電力の配線組み換えなどが登場する。 だが、それのどれもが良くも悪くもシンプルになっているので、硬派なパズルを求める方には物足りなく感じるかもしれない。 おそらく、思想としては、プレイヤー側に、アクションと探索面に集中するように作られているという印象を受けた。強化システムとクラフト
◆ 本作ではセーブポイントに配置されている機器で素材、弾薬や回復アイテムの購入、売却、装備品のアップグレードなどを行う事が可能となっている。 敵を撃破、あるいは探索を通して入手できる通貨を消費する事で各種アイテムの購入と武器の強化を行え、HPの最大値やインベントリの枠、トーチの最大携帯可能数といった一部の機能は「コア」と呼ばれるアイテムを消費する事で強化可能となっている。 弾薬も購入可能であるため、そういった点ではかなりユーザーフレンドリーな仕様と言えるだろう。 コアを使用した強化意外は「リセット」可能であり、使用済みの通貨が返却される。 そのため、試しに色々と強化を行う事が可能である点もありがたい。 クラフトは探索を通して入手できる素材を消費して弾薬や回復用アイテムを作成するというわかりやすいシステムだ。 素材となるアイテムは通常のインベントリとは異なる箇所に“溜まっていく”が、初期は所持可能な最大数が少ないため、早い段階で最大値を強化する事をオススメする。 素材が少し足りない場合は拠点で足りない分のみを購入して弾薬を作成したりと、こちら方面でもプレイヤースキルが活かせる点が面白い。 冒頭でも述べたが、本作は全体的に同ジャンルの名作から影響を受けており、この強化システムとクラフトは「Dead Space」+「サイコブレイク」シリーズからの影響だろう。 まあ、今では様々な作品に採用されているわけだが。ストーリーテリング
◆ タイムトラベルを絡めた物語や様々な古典の名作的映画作品から影響を受けたレトロフューチャーな映像表現、物語の重要な部分自体は面白く引き込まれる。 だが、残念ながらストーリーテリングに難があり、序盤の終わりから終盤の初めごろまで、物語に関連した重要となる新たな情報が特に出てこない事と、登場人物達の殆どが中身のない会話で“水増し”を行ってくる点が気になった。 ゲームの長さ的に濃いが短い内容の物語を唯々引き伸ばしてしまっている印象だ。 そのため、物語は中盤辺りから進展がなく、かなり退屈になる。 登場人物も重要かつ印象に残るキャラクターは主人公と途中で登場するもう一人だけなので、余計に物語の進行速度が気になる。 探索を通して入手できる、物語の背景や住民の状態が分かる収集要素、手紙や日記、音声ログなどに関しても同様で、基本的には新たな情報や考察に利用できる物は少なく、物語の進展と同じようなタイミングでこちらも情報が解禁されていく。 物語全体を通して、重要な部分だけを繋げてみた場合、そこら辺は通常に面白いだけに残念でならない。デザイン
◆ 『Cronos: The New Dawn』における敵のデザインは『人が歪に融合した』かのような、ボディホラー系映画作品のそれを彷彿とさせる味のあるデザインとなっている。 単体やいくつかの敵に関してはそれで問題は無いのだが、言葉を選ばないのであれば、序盤に登場する敵の多くは外見の変化に乏しく、雑なバリエーションが多い。 一番最初に登場する敵、初期に登場する敵のマイナーチェンジに近い。 例えば、通常の敵が融合した強力な個体は肩にトゲ+腕が多めに生えている、特定部位にダメージが通りにくい敵はその部位が石化している、体力の高い強い敵は大きく太っている、というように特徴があるのだが、初期に登場した敵にその特徴がプラスされただけとなっている。 特に強力になっただけの個体は、暗いエリアやパッと見で外見の特徴を把握し辛く、慣れるまでどちらの敵か分からないという事が発生する。 また、他の敵も基本的には外見やデザインがマイナーチェンジや大きさの変化になるため、印象に残り難い。 非常にもったいない。 ただし、その分、最初のボスはともかく、他のボスに関してはイイ感じのデザインが為されている。 余談となるが、「Dead Space」が死体が怪物に変貌するのに対して、本作は敵の死体が他の死体と融合する事によって新たな怪物が誕生する。 影響元であるそちらの『逆』と他の項目でも述べた映画作品の要素をミックスしたデザインという面白い取り組みとなっている。やや玄人向け
◆ 弾薬の節約、強化の仕組み、地形を利用した戦闘、インベントリ管理など、そのどれもが、良くも悪くも同ジャンルの作品をある程度理解したプレイヤー向けに作られている。 例えば、筆者の初回プレイを参考として挙げると、他作品の経験を活かしてプレイしていたため、かなり弾薬が節約でき、さらに通貨も余り気味になっていた。 だが、プレイヤーによっては逆に初見プレイでは弾薬が枯渇するという印象を受ける可能性が高い。 それもそのはずで、先ほど述べたように、ジャンルに精通している前提で難易度が調整されている節がある。 本レビューの別の項目でそれぞれ軽く触れているが、このような形となっている。 『敵の足を撃ち、転ばせ近接でトドメをさす』、『地形のオブジェクトを利用して敵を倒す』、『敵を一か所に集めてまとめて貫通武器/トーチで倒す』『武器の強化は敵を素早く倒し、弾薬を節約するために攻撃力を優先的に強化』、『システムの悪用』等と戦闘面に関してだけでも色々と出来るのだが、これらの殆どは他の同ジャンル作品で覚えるものであり、初見ではなかなかできない。 通貨とインベントリ周りに関しても同様で『インベントリ枠の強化優先』『次に素材の最大値増加』『回復薬は売り、HPが少なくなったら最大HP上昇強化で回復』『余った弾薬は売り、攻撃力強化』等と、やはり他作品をプレイしている前提のような作りだ。 特に通貨が余る部分が重要で、本作は弾薬とクラフト素材を購入できるので、システムを理解すれば、基本的には弾薬が無くなるという状態が殆ど発生しない。 それこそ、ジャンルに慣れていない場合のみとなる。 こういった調整はある程度慣れたプレイヤーにとってはバランスが良く、スキルを活かせるために面白いのだが、慣れていない方には逆に難しいと感じられる可能性も高いので、“良くも悪くも”と表現させていただいた。 それに加えて、もう一つ付け足すならば、完全な玄人向けかというと、そうでもない。 なぜならば、それらのどの要素も影響元作品のそれと比べると特化型ではないからだ。 そのため、それらと比べると、やや“深みが足りない”と感じる可能性もある。----------------------【良い点】----------------------
+ 様々な同ジャンル作品の要素を上手くミックスした各種要素。 + 戦略的な戦闘とそれを活かせるレベルデザイン。 + 探索する価値のあるマップ作り。----------------------【悪い点】----------------------
- 重要部分以外は単調なストーリーテリング。 - 変化の乏しい敵デザイン。 - 良くも悪くも玄人向け。-----------------------【総評】----------------------
真新しい要素こそ無いものの、『Cronos: The New Dawn』は、「Dead Space」や「SILENT HILL 2(リメイク版)」、「サイコブレイク」などの名作、映像面ではSFホラー映画作品などから影響を受けつつ、それらの要素を丁寧にミックスした良作のSFサバイバルホラー作品となっている。 戦闘における「チャージ」要素や死体の処理に必須となる「トーチ」、地形や時間操作を活かした戦略的なレベルデザインなど、プレイヤーの工夫を引き出す仕組みが豊富で、同ジャンル経験者であれば“深く”楽しめる作りだ。 一方で、ストーリーの進行速度や会話の水増し感、敵デザインのバリエーション不足など、惜しい点も散見され、特に物語面では序盤と終盤の盛り上がりに対して中盤が間延びしてしまい、印象を弱めている事が残念だ。 また、戦闘/探索/インベントリ管理などがある程度ジャンルに慣れたプレイヤーを前提に調整されているため、初心者にとっては難しく感じられる部分もある。 初心者でもプレイに大きな支障はないが、総じて、本作は“ホラーアクションに慣れたプレイヤーが挑むことで真価を発揮する”作品ともいえる。プレイ動画をアップしているので、本作が気になった方はこちらを参考までにどうぞ。https://www.youtube.com/watch?v=s93uMOyOVPU
他にもアクションやメトロイドヴァニア系作品をSteamキュレータープラットフォーマーズで、ローグライク作品を[url="https://store.steampowered.com/curator/37908283"]ローグライクゲーマーズ
2 votes funny
76561198008849076
Recommended32 hrs played (20 hrs at review)
日本語環境におけるフリーズについて
他の方のレビューにも記載されていますが、レコーダーに記録されたオーディオログや、オレンジ色のオブジェクトに触って音声が再生される際に「日本語字幕を表示させている」と高確率でゲームがフリーズします(アプリケーションを強制終了するしかなくなる)。
いくつか回避策はありますが、堅実なのは「(オーディオログなどに触る前に)その場で一時的に言語設定を英語に変更する」でフリーズしないことを確認しています。音声をスキップすることでも回避できますが、そもそも再生した瞬間にスキップをする暇すらなくフリーズする場合があり、回避が間に合わないことがあるためです。
なお、英語設定で再生された内容は後からデータベースで日本語翻訳されたものを読み返すことができるので、全スルーするという回避方法はおすすめしません。
※開発チームには報告済
https://steamcommunity.com/app/2101960/discussions/0/604166319349270041/
(Steam Communityに報告後、メールでも報告して調査依頼済)
1 votes funny
76561199760507479
Recommended17 hrs played (4 hrs at review)
ゲーム内容はめちゃくちゃ面白いです。
グラフィックはもちろん綺麗です。サウンドが物凄くリアルです。
探索、謎解きいいですね!
コントローラーでの操作性も良いです。
一部序盤で同じ場所で同じアクションで必ずフリーズするところがありました。
そこはスルーする事で先に進みました。今のところ不具合はその1か所だけです。
YouTubeに動画アップしてます。気になる方は見てみて下さい。
www.youtube.com/@reviver_98
1 votes funny
Cronos: The New Dawn
 Sep 5, 2025
Sep 5, 2025 Sep 3, 2025
Sep 3, 2025 Sep 5, 2025
Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
Sep 4, 2025

76561199004086690
Not Recommended16 hrs played (5 hrs at review)
面白いんですが
改善点が多いですかね。
2 votes funny
76561197993473791
Recommended19 hrs played (19 hrs at review)
一部の環境で発生する再現性の高いバグを発見したので回避方法を先に書いておきます。
【フリーズバグの回避方法】
①:『音声ログ再生時のフリーズ』
・音声ログを拾ってすぐにログの再生をキャンセル/終了する事で回避可能。
②:『出口(ファストトラベル)に戻る時のフリーズ』
・使用せずに歩いて戻る(戻れる場合)
※上記で回避できない場合は言語を一旦英語に変更でいけるはず!
こちらはアドバンスドアクセスで発生しているバグなので、すぐに修正されると思いますが、参考になれば何よりです。
ぜひ楽しんでください!
我らが使命によりて。
----
Flydigi Direwolf 2コントローラーを使用。
プレイ動画をアップしているので、本作が気になった方はこちらを参考までにどうぞ。https://www.youtube.com/watch?v=s93uMOyOVPU
あらすじとゲーム概要
◆ 「SILENT HILL 2(リメイク版)」や「The Medium」で知られる開発元の贈る、三人称視点のSFサバイバルホラー作品。 東欧の残忍性とレトロフューチャーテクノロジーが融合した過酷な世界を舞台に、ねじれたタイムトラベル、過去と未来を行き来する手に汗握るストーリーが展開される。 プレイヤーは謎に包まれた共同体のエージェントとして旅し、80年代のポーランドに連れ戻す特殊な時間の裂け目を見つけるため、未来の荒れ地を捜索するという任務を請け負う。 荒廃した未来の世界で戦い抜き、悪夢のように融合するクリーチャーが出現した理由、人類を滅ぼした黙示録の真相を探るため、時を遡って魂を狩れ。 物語や演出面では「エイリアン」シリーズや「遊星からの物体X」などの古典的名作から影響を受けているようで、レトロフューチャーな表現だけではなく、当時のボディホラーを彷彿とさせる映像表現も登場する。 さらに開発元が本作の舞台であるポーランド出身という事もあり、80年代のポーランド、共産党支配の抑圧、労働者/市民による抵抗、経済危機と社会不安、冷戦期の東欧の中でもとりわけ激動に満ちた時代の“その場所”の表現が非常に上手く取り入れらている。 アクションやシステム面に関しては、各項目でそれぞれ詳細に解説するが、本作はシステム面で「Dead Space」シリーズから強く影響を受けているだけではなく、三人称視点のシューター要素、敵を殴る/踏みつける、敵を燃やす、探索周り、硬派なインベントリ管理、装備の強化要素などなど、全体的に「Dead Space」、「SILENT HILL 2(リメイク版)」、「サイコブレイク」等の同ジャンルの名作のシステムを、良い意味で、ミックスした内容となっている。戦闘システム
◆ 基本的な攻撃用のアクションは銃を撃つ、殴る/踏み付けるとなるが、この他に自身の周りを燃やすトーチ、敵に爆弾を設置するパイヤーなども物語を進める事で使用可能となる。 初期から主人公が使用可能である銃「ソード」、ピストル的な性能のこの銃は非常に優秀で、チャージする事によって威力が上昇し、さらに敵を貫通するようになる。 探索を通じでショットガン、アサルトライフルの様な銃などを入手できるが、このチャージを利用したアクションは本作の殆どの武器で使用できるので、慣れておくと良いだろう。 ちなみに、武器の総数自体は少ないが、それぞれでしっかりと状況によって“使える”ため、あまり気になる事は無いはずだ。 同ジャンルの他の作品と同様に、敵の足などの部位を撃ち抜くことで転ばせるといった事が可能で、転んだ敵に踏みつけでダメージを与えて弾薬を節約するといった事も勿論可能だ。 ただし、注意点としては、初期状態の主人公の近接攻撃は威力が非常に弱いため、ある程度敵のHPの残量を把握していないと起き上がった敵から逆にダメージをもらってしまう可能性がある。 ネタバレになってしまうため詳細は控えるが、物語/探索を進める事で近接攻撃の威力を上昇させる事ができるので、そちらを有効活用すると良いだろう。 部位を攻撃する事はもちろん、本作の特徴ともいえる武器の「チャージ」を絡めた戦闘は独特で面白く、チャージを行う必要がある戦闘では、同ジャンルの他の作品とは別の意味で敵との間合いの取り合いや、チャージにかかる時間の把握、そういった部分が重要となり、プレイヤースキルが問われる箇所がある点が魅力的だ 少し話がズレるが、敵の部位を狙うと言えば、エイム時の本作の主人公は禁断症状のヤ○中患者の如く手が震えるため、後ほど解説する武器の強化である程度は「安定性」の強化を行う事をオススメする。 話を戻そう。 この他にも、「トーチ」と呼ばれる自身の周りに炎を発生させる武器も存在し、こちらの弾薬は「一つ」まで、セーブポイントで無料で補充可能となっている。 本作に登場する敵は他の敵の死体と融合し、より強力な敵へと変貌する。 それを発生させないためには死体を燃やす必要があり、トーチはそういった死体処理にも使用可能だ。 だが、実際にはトーチ使用中はちょっとした無敵時間が発生する事と、ボスを含め、殆どの敵は炎の影響で一時的に「スタン(のような)」状態になるため、緊急時やまとめて敵を撃破したい時等に、いわゆる「ボム」の様に使用される事が多い。 少し“コツ”の様な話になるが、セーブポイントに戻る事でトーチを補充できるため、時間はかかるが、一部のエリアではそれを悪用して楽に進める事も可能だ。 また、敵はセーブポイントに入れない仕様になっているので、扉の前まで連れて行き、そちらの仕様もついでに悪用すると良いだろう。 本題に戻ろう。 トーチ以外では物語の中盤で「パイヤー」と呼ばれる発射できる接着型爆弾も使用できる。 基本的にはトーチと同じように使用する形となっているが、こちらは拠点で補充されないため、弾薬を見つけるか、自身で作成する必要がある。 戦闘に関連した要素としては、戦闘が発生するエリア/レベルデザインも秀逸で、地形を上手く利用、活かすことによって楽に敵を撃破できたり、弾薬を節約する事ができる。 エリアの様々な箇所に配置されたオブジェクトの利用や、時間を巻き戻す能力を利用して爆発するオブジェクトを“再生”し、敵をおびき寄せてまとめて倒すといった事が可能だ。 ちなみに、本作の主人公は爆発に巻き込まれてもダメージを負わない仕様となっているので、殴ったり踏みつけによってこれらのオブジェクトを起爆すると弾薬を節約する事が可能だ。 こうったプレイヤー側意外の要素としては、敵のAIがなかなか優秀である点も本作の魅力と言えるだろう。 もちろんゲームであるため悪用したり、妙な地形に敵を嵌めるといった事も可能ではあるが、敵はある程度マップの地形を把握しており、最短距離でプレイヤーを狙う、先に死体と融合をしようとする、などと単調にならないような挙動を取ってくる。 そのため、プレイヤー側は敵の位置の把握や融合の阻止といった、攻撃以外の面でも頭を使う必要が出てくる。 特に後半は、同時に出現する敵の数も多くなるため、その点でもさらに面白くなってくる。 戦闘が発生するエリアも様々なモノが登場し、迷宮の様に複数の道が繋がる狭い閉塞的な空間、一本道の長い廊下、砂嵐によって視界の悪い場所、非常に広くて何処から敵が出現するか分からない場所などなど、プレイヤーを飽きさせない工夫がゲームの最後まで為されている。 戦闘面における人を選ぶ点も挙げるならば、主人公の動きがやや“重たい事”だろう。 主人公は重量級のスーツを着込んでいるのでそれが自然ではあるが、同ジャンルの他作品と比べて動きが遅く、また回避アクションも存在しないので、プレイヤーによっては違和感を覚えるかもしれない。 ただし、それによって理不尽なシチュエーションが発生するという事はなく、その動きを前提としたエリア構成/レベルデザインが為されている。探索とマップ作り
◆ レトロフューチャー感漂う歪にねじれ、荒廃したダークな未来世界。 次元の裂け目を通じて訪れる事の可能な、日常の風景が垣間見えるが、明らかに異常な何かが浸食を始めている80年代のポーランド。 そういったギャップの魅せ方が上手く、ビジュアル面でも非常に魅力的となっている。 「The Medium」の開発元だけあり、一瞬で場面、地形などが変化するといった演出も非常に上手い。 別の項目で述べた戦闘が発生するエリアの作りの巧さもさることながら、探索周りに関しては、しっかりとプレイヤーが探索を行う事によって隠された部屋やエリアを発見することができ、その中には様々な有用なアイテムが配置されていたりと、探索する面白さ、発見する楽しさ、そういった要素を良く理解した作りだ。 探索時に注意する必要がある点としては、初期状態では、インベントリの枠が非常に少ない事だ。 そのため、多くの弾薬や回復薬を持ち歩くと、探索時に発見したアイテムを回収できないという事態が発生する。 殆どの場所には再び立ち寄る事ができるが、何か所かは戻れないので、探索時にはその点に注意すると良いだろう。 それに加えて、後ほど解説する強化によってインベントリの枠を拡張できるため、そちらを優先的に行う事をオススメする。 注意点と言えば、同ジャンルの他の作品がそうであるように、本作では物語の進行や探索時にいくつかのパズルが登場するが、必要最低限、さらに簡単なモノとなっている。 登場するパズル要素は、アイテムの配置系、パスワード系などの良く見るものから、特定の物体の時間を巻き戻して通行可能にする、物語を進める事で入手できる磁力を利用したブーツを使用して特殊な足場へと“飛び回る”モノや、特殊な弾を利用した電力の配線組み換えなどが登場する。 だが、それのどれもが良くも悪くもシンプルになっているので、硬派なパズルを求める方には物足りなく感じるかもしれない。 おそらく、思想としては、プレイヤー側に、アクションと探索面に集中するように作られているという印象を受けた。強化システムとクラフト
◆ 本作ではセーブポイントに配置されている機器で素材、弾薬や回復アイテムの購入、売却、装備品のアップグレードなどを行う事が可能となっている。 敵を撃破、あるいは探索を通して入手できる通貨を消費する事で各種アイテムの購入と武器の強化を行え、HPの最大値やインベントリの枠、トーチの最大携帯可能数といった一部の機能は「コア」と呼ばれるアイテムを消費する事で強化可能となっている。 弾薬も購入可能であるため、そういった点ではかなりユーザーフレンドリーな仕様と言えるだろう。 コアを使用した強化意外は「リセット」可能であり、使用済みの通貨が返却される。 そのため、試しに色々と強化を行う事が可能である点もありがたい。 クラフトは探索を通して入手できる素材を消費して弾薬や回復用アイテムを作成するというわかりやすいシステムだ。 素材となるアイテムは通常のインベントリとは異なる箇所に“溜まっていく”が、初期は所持可能な最大数が少ないため、早い段階で最大値を強化する事をオススメする。 素材が少し足りない場合は拠点で足りない分のみを購入して弾薬を作成したりと、こちら方面でもプレイヤースキルが活かせる点が面白い。 冒頭でも述べたが、本作は全体的に同ジャンルの名作から影響を受けており、この強化システムとクラフトは「Dead Space」+「サイコブレイク」シリーズからの影響だろう。 まあ、今では様々な作品に採用されているわけだが。ストーリーテリング
◆ タイムトラベルを絡めた物語や様々な古典の名作的映画作品から影響を受けたレトロフューチャーな映像表現、物語の重要な部分自体は面白く引き込まれる。 だが、残念ながらストーリーテリングに難があり、序盤の終わりから終盤の初めごろまで、物語に関連した重要となる新たな情報が特に出てこない事と、登場人物達の殆どが中身のない会話で“水増し”を行ってくる点が気になった。 ゲームの長さ的に濃いが短い内容の物語を唯々引き伸ばしてしまっている印象だ。 そのため、物語は中盤辺りから進展がなく、かなり退屈になる。 登場人物も重要かつ印象に残るキャラクターは主人公と途中で登場するもう一人だけなので、余計に物語の進行速度が気になる。 探索を通して入手できる、物語の背景や住民の状態が分かる収集要素、手紙や日記、音声ログなどに関しても同様で、基本的には新たな情報や考察に利用できる物は少なく、物語の進展と同じようなタイミングでこちらも情報が解禁されていく。 物語全体を通して、重要な部分だけを繋げてみた場合、そこら辺は通常に面白いだけに残念でならない。デザイン
◆ 『Cronos: The New Dawn』における敵のデザインは『人が歪に融合した』かのような、ボディホラー系映画作品のそれを彷彿とさせる味のあるデザインとなっている。 単体やいくつかの敵に関してはそれで問題は無いのだが、言葉を選ばないのであれば、序盤に登場する敵の多くは外見の変化に乏しく、雑なバリエーションが多い。 一番最初に登場する敵、初期に登場する敵のマイナーチェンジに近い。 例えば、通常の敵が融合した強力な個体は肩にトゲ+腕が多めに生えている、特定部位にダメージが通りにくい敵はその部位が石化している、体力の高い強い敵は大きく太っている、というように特徴があるのだが、初期に登場した敵にその特徴がプラスされただけとなっている。 特に強力になっただけの個体は、暗いエリアやパッと見で外見の特徴を把握し辛く、慣れるまでどちらの敵か分からないという事が発生する。 また、他の敵も基本的には外見やデザインがマイナーチェンジや大きさの変化になるため、印象に残り難い。 非常にもったいない。 ただし、その分、最初のボスはともかく、他のボスに関してはイイ感じのデザインが為されている。 余談となるが、「Dead Space」が死体が怪物に変貌するのに対して、本作は敵の死体が他の死体と融合する事によって新たな怪物が誕生する。 影響元であるそちらの『逆』と他の項目でも述べた映画作品の要素をミックスしたデザインという面白い取り組みとなっている。やや玄人向け
◆ 弾薬の節約、強化の仕組み、地形を利用した戦闘、インベントリ管理など、そのどれもが、良くも悪くも同ジャンルの作品をある程度理解したプレイヤー向けに作られている。 例えば、筆者の初回プレイを参考として挙げると、他作品の経験を活かしてプレイしていたため、かなり弾薬が節約でき、さらに通貨も余り気味になっていた。 だが、プレイヤーによっては逆に初見プレイでは弾薬が枯渇するという印象を受ける可能性が高い。 それもそのはずで、先ほど述べたように、ジャンルに精通している前提で難易度が調整されている節がある。 本レビューの別の項目でそれぞれ軽く触れているが、このような形となっている。 『敵の足を撃ち、転ばせ近接でトドメをさす』、『地形のオブジェクトを利用して敵を倒す』、『敵を一か所に集めてまとめて貫通武器/トーチで倒す』『武器の強化は敵を素早く倒し、弾薬を節約するために攻撃力を優先的に強化』、『システムの悪用』等と戦闘面に関してだけでも色々と出来るのだが、これらの殆どは他の同ジャンル作品で覚えるものであり、初見ではなかなかできない。 通貨とインベントリ周りに関しても同様で『インベントリ枠の強化優先』『次に素材の最大値増加』『回復薬は売り、HPが少なくなったら最大HP上昇強化で回復』『余った弾薬は売り、攻撃力強化』等と、やはり他作品をプレイしている前提のような作りだ。 特に通貨が余る部分が重要で、本作は弾薬とクラフト素材を購入できるので、システムを理解すれば、基本的には弾薬が無くなるという状態が殆ど発生しない。 それこそ、ジャンルに慣れていない場合のみとなる。 こういった調整はある程度慣れたプレイヤーにとってはバランスが良く、スキルを活かせるために面白いのだが、慣れていない方には逆に難しいと感じられる可能性も高いので、“良くも悪くも”と表現させていただいた。 それに加えて、もう一つ付け足すならば、完全な玄人向けかというと、そうでもない。 なぜならば、それらのどの要素も影響元作品のそれと比べると特化型ではないからだ。 そのため、それらと比べると、やや“深みが足りない”と感じる可能性もある。----------------------【良い点】----------------------
+ 様々な同ジャンル作品の要素を上手くミックスした各種要素。 + 戦略的な戦闘とそれを活かせるレベルデザイン。 + 探索する価値のあるマップ作り。----------------------【悪い点】----------------------
- 重要部分以外は単調なストーリーテリング。 - 変化の乏しい敵デザイン。 - 良くも悪くも玄人向け。-----------------------【総評】----------------------
真新しい要素こそ無いものの、『Cronos: The New Dawn』は、「Dead Space」や「SILENT HILL 2(リメイク版)」、「サイコブレイク」などの名作、映像面ではSFホラー映画作品などから影響を受けつつ、それらの要素を丁寧にミックスした良作のSFサバイバルホラー作品となっている。 戦闘における「チャージ」要素や死体の処理に必須となる「トーチ」、地形や時間操作を活かした戦略的なレベルデザインなど、プレイヤーの工夫を引き出す仕組みが豊富で、同ジャンル経験者であれば“深く”楽しめる作りだ。 一方で、ストーリーの進行速度や会話の水増し感、敵デザインのバリエーション不足など、惜しい点も散見され、特に物語面では序盤と終盤の盛り上がりに対して中盤が間延びしてしまい、印象を弱めている事が残念だ。 また、戦闘/探索/インベントリ管理などがある程度ジャンルに慣れたプレイヤーを前提に調整されているため、初心者にとっては難しく感じられる部分もある。 初心者でもプレイに大きな支障はないが、総じて、本作は“ホラーアクションに慣れたプレイヤーが挑むことで真価を発揮する”作品ともいえる。プレイ動画をアップしているので、本作が気になった方はこちらを参考までにどうぞ。https://www.youtube.com/watch?v=s93uMOyOVPU
他にもアクションやメトロイドヴァニア系作品をSteamキュレータープラットフォーマーズで、ローグライク作品を[url="https://store.steampowered.com/curator/37908283"]ローグライクゲーマーズ
2 votes funny
76561198008849076
Recommended32 hrs played (20 hrs at review)
日本語環境におけるフリーズについて
他の方のレビューにも記載されていますが、レコーダーに記録されたオーディオログや、オレンジ色のオブジェクトに触って音声が再生される際に「日本語字幕を表示させている」と高確率でゲームがフリーズします(アプリケーションを強制終了するしかなくなる)。
いくつか回避策はありますが、堅実なのは「(オーディオログなどに触る前に)その場で一時的に言語設定を英語に変更する」でフリーズしないことを確認しています。音声をスキップすることでも回避できますが、そもそも再生した瞬間にスキップをする暇すらなくフリーズする場合があり、回避が間に合わないことがあるためです。
なお、英語設定で再生された内容は後からデータベースで日本語翻訳されたものを読み返すことができるので、全スルーするという回避方法はおすすめしません。
※開発チームには報告済
https://steamcommunity.com/app/2101960/discussions/0/604166319349270041/
(Steam Communityに報告後、メールでも報告して調査依頼済)
1 votes funny
76561199760507479
Recommended17 hrs played (4 hrs at review)
ゲーム内容はめちゃくちゃ面白いです。
グラフィックはもちろん綺麗です。サウンドが物凄くリアルです。
探索、謎解きいいですね!
コントローラーでの操作性も良いです。
一部序盤で同じ場所で同じアクションで必ずフリーズするところがありました。
そこはスルーする事で先に進みました。今のところ不具合はその1か所だけです。
YouTubeに動画アップしてます。気になる方は見てみて下さい。
www.youtube.com/@reviver_98
1 votes funny